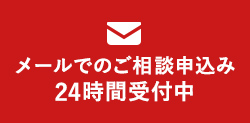【建物賃貸借契約条項解説】7 敷金一般
1.はじめに
敷金とは、賃貸借契約に基づく金銭債務を担保する目的で、賃借人から賃貸人に預託される金員のことです。なお、改正民法第622条の2においては、敷金を、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されています。
住居用賃貸借契約では、契約時に1か月~数か月分の敷金を預託することが一般的かと思われます。
2.敷金の返還時期
敷金は、賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる、賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものです。したがって、賃貸人は、賃貸借の終了後家屋の明渡がされた時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額につき返還義務を負担します( 最判昭48.2.2民集27-1-80)。
したがって、契約終了に伴う建物明渡義務と同時履行の関係に立ちません( 最判昭49.9.2民集28-6-1152)。そして、敷金の返還が無いからと言って、建物の明渡しを拒否することも原則としてできません。
3.敷金の充当
賃貸人は、敷金を債務に充当することができます。逆に、賃借人が、敷金を未払債務に充当することを求めることはできません(改正民法622条の2第2項)。
敷金を債務に充当した場合、賃貸人は不足した敷金を賃借人に対してその預託を求めることができる旨(又は、当然に賃借人に充当義務が発生する旨)、規定されることがほとんどだと思われます。逆に、不足分の預託を求めることができる旨の規定がない場合には、原則として追加の敷金の充当を求めることはできないと考えられます。その意味で、充当義務又は充当を求めることができる旨の規定は必須です。
次のページ: 8.敷金返還債務の承継
目次:建物賃貸借契約条項解説
- 賃貸借の目的物
- 契約期間・更新条項
- 使用目的
- 更新料
- 賃料等の支払時期・支払方法
- 賃料改定・賃料増減請求
- 敷金一般(本ページ)
- 敷金返還債務の承継
- 館内規則・利用規約等
- 遅延損害金
- 賃貸人の修繕義務
- 契約の解除・信頼関係破壊の法理
- 保証金
- 賃借人たる地位の移転
- 原状変更の原則禁止
- 善管注意義務及び損害賠償
- 連帯保証人
- 反社会的勢力の排除
- 当事者双方からの期間内解約条項