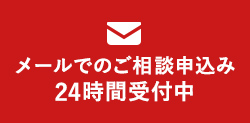【建物賃貸借契約条項解説】8 敷金返還債務の承継
1 はじめに
建物所有権の移転(オーナーチェンジ)等に伴い賃貸人の地位が移転した場合の敷金返還債務の帰趨は、最高裁判例が存在するとともに、改正民法により明文化されています(改正民法605条の2第4項)。
敷金返還債務が移転するのか否か、どの範囲で移転するのか、について適切な対応をとらないと、明渡の際に賃借人とトラブルになる可能性もあります。特に注意が必要です。
2 判例と改正民法の内容
- 建物所有権が移転した場合、賃貸人たる地位は当然に旧所有者から新所有者に移転するとともに、旧所有者に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される、というのが判例です( 最判昭44.7.17民集23-8-1610)。
- 他方で、旧所有者が敷金返還債務を完全に免れるかという点に関し明確に判示した判例はありませんし、現行民法にも規定はありません。
- 改正民法においては、賃借人が対抗要件を備えた賃貸借契約において、当該不動産が譲渡された場合には、賃貸人たる地位はその譲受人に移転すると定められています(改正民法605条の2第1項)。このとき、敷金返還債務も譲受人が承継する(同第4項)とされています。他方で、旧所有者が敷金返還債務を免れるのか規定はありません。また、旧賃貸人に対する未払債務に充当されるか否かについての規定もありません。
3 オーナーチェンジの際における望ましい対応
- オーナーチェンジの際の敷金返還債務の帰趨について、明確な規定はありません。したがって、敷金返還債務の帰趨やその範囲については、売買当事者間で明確に定める必要があります。
- 加えて、旧所有者が敷金返還義務を免れるためには、賃借人より同意を取得することが望ましいと思われます(免責的債務引受であるため)。多数の賃借人がいる物件では取得すること自体が大変ですが、明渡の際に新所有者とトラブルになったときなど、敷金返還を求められるリスクが否定できません。特に敷金が高額の場合には、面倒でも個別に同意を取得することをお勧めします。
次のページ:9.館内規則・利用規約等
目次:建物賃貸借契約条項解説
- 賃貸借の目的物
- 契約期間・更新条項
- 使用目的
- 更新料
- 賃料等の支払時期・支払方法
- 賃料改定・賃料増減請求
- 敷金一般
- 敷金返還債務の承継(本ページ)
- 館内規則・利用規約等
- 遅延損害金
- 賃貸人の修繕義務
- 契約の解除・信頼関係破壊の法理
- 保証金
- 賃借人たる地位の移転
- 原状変更の原則禁止
- 善管注意義務及び損害賠償
- 連帯保証人
- 反社会的勢力の排除
- 当事者双方からの期間内解約条項