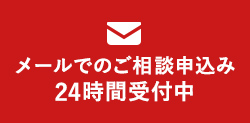【家賃滞納・建物明渡専門弁護士による契約条項解説】17 連帯保証人
【条項例】
第〇条(連帯保証人)
1 連帯保証人は、本契約に基づく賃借人の賃貸人に対する一切の債務について、本契約書に記載された賃料及び共益費相当額の2年分を限度として、賃借人と連帯して履行の責めを負う。
2 賃借人又は連帯保証人は、連帯保証人が以下の各号に該当するときは、直ちに書面又はメールにより賃貸人へ通知する。
(1) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき
(2) 破産手続・特別清算・特定調停・民事再生手続・会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自らこれの申し立てをしたとき
(3) 死亡したとき
(4) 後見・補佐・補助開始の審判又は任意後見契約がなされたとき
3 連帯保証人が前項のうち一つにでも該当した場合には、賃借人は直ちに他の連帯保証人を選定したうえで、賃貸人の承諾を得なければならない。
4 連帯保証人は、本契約が更新された場合及び賃料、共益費その他賃借人が負担する一切の費用に変更があった場合にも、第1項に定める極度額の限度で賃借人と連帯して履行する責めを負うものとする。
【解説】
1 趣旨
本条は、賃借人の連帯保証人に関して定めた規定です。連帯保証人を定めるのは、賃借人が家賃滞納を生じさせた場合、また、何らかの理由で賃貸人に損害を生じさせるなど、賃貸人に対する何らかの債務不履行を生じさせた場合に、その履行(賠償責任)を担保することにあります。
気を付けなければならないのは、連帯保証人が担保する債務は、明け渡しに関する債務を含まないという点です。例えば、賃借人が家賃滞納を理由に契約を解除され場合に、連帯保証人に建物明け渡しを求めることはできません。建物の明け渡しは、賃借人しか履行できないものだからです。
近年は家賃保証会社による機関保証が主流になっていますが、機関保証だけではカバーできない損害も生じ得ます。また、賃借人に家賃滞納が生じた場合や、明渡請求に至った場合に連帯保証人の協力により解決に至ることも多々あります。このような観点から、資力のある連帯保証人を確保する必要性が低下したとはいえません。
2 条項の内容
(1) 第1項について
民法第447条の規定を明文化したものです。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するものとされています。その点を明文化したものです。
もう1点注意点があります。賃貸借契約について個人が保証人になる場合には極度額を定めなければなりません(民法第465条の2。なお、法人が保証人になる場合に極度額の定めは不要です)。この極度額の定めがない場合には、保証契約自体が無効となりますので、必ず盛り込む必要があります。なお、極度額の定めは、金額が確定できていれば、必ずしも確定金額を記載する必要はないとされています。例えば条項例のように、「本契約書に記載のある賃料及び共益費相当額の2年分」という記載でも、金額が算定できれば差し支えないとされています。
(2) 第2項と第3項について
第2項と第3項は、連帯保証人の欠格事由について定めた規定です。
連帯保証は、家賃滞納や明渡訴訟など、トラブルが生じた際に備えて行われるものですから、資力に問題が生じた場合にはその交代を求める必要があります。第2項で報告義務を課し、第3項で連帯保証人の変更義務を課しています。但し、気を付けなければいけないのは、「変更を求めたからといって必ずしも変更に至るとは限らない」という点です。賃借人が他に保証人を頼める人がいない場合には、連帯保証人の交代には至らないので注意が必要です。
(3) 第4項について
第4項は、連帯保証人の責任の範囲を定めたものです。
保証人は、更新後の賃貸借契約に基づく賃借人の債務についても責任を負うというのが判例です(最判平成9年11月13日判決判時1633号81頁)。他方で、主債務の内容が保証契約の締結後に重くなった場合に保証人の責任は加重されないというのが確定した判例通説であり、民法にもその旨規定されました(第448条第2項)。この考え方だと、賃貸人と賃借人との合意により賃料等が増額された場合には、連帯保証人は増額分の滞納賃料の支払債務を負わない、との考え方になりそうです。
しかし、民法後に契約を締結する場合、極度額の設定がなされたことから、連帯保証人の責任はこの極度額の範囲で責任を負うわけですから、この範囲であれば「負担が加重された」といえないと考えます。したがって、民法施行後は極度額の範囲であれば、その責任を負うと考えます。
以上の考え方に従い、条項例では民法施行前とその後で文面を分けています。
3 滞納賃料の回収に備えた対応
連帯保証人に対し、家賃滞納分の保証債務履行請求訴訟を提起する場合に多い主張が、「印鑑を押した覚えがない」つまり、保証否認です。このような主張を避けるために、契約時においては、連帯保証人に実印を押捺してもらうとともに、印鑑証明書を取得する必要があります。
改正民法後においては、連帯保証人に対する情報提供義務が課せられています。賃貸人としては、この際に保証人から情報確認提供を受けた旨の書面を求めることになりますが、この際に自署にて署名・押印してもらうことも一つの対策になると思われます。
※2021/10/14 改正民法が施行されたことに伴い、記載を変更しました。
次のページ: 18.反社会的勢力の排除
目次:建物賃貸借契約条項解説
- 賃貸借の目的物
- 契約期間・更新条項
- 使用目的
- 更新料
- 賃料等の支払時期・支払方法
- 賃料改定・賃料増減請求
- 敷金一般
- 敷金返還債務の承継
- 館内規則・利用規約等
- 遅延損害金
- 賃貸人の修繕義務
- 契約の解除・信頼関係破壊の法理
- 保証金
- 賃借人たる地位の移転
- 原状変更の原則禁止
- 善管注意義務及び損害賠償
- 連帯保証人(本ページ)
- 反社会的勢力の排除
- 当事者双方からの期間内解約条項