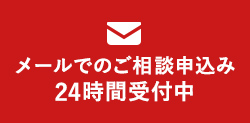【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (5)強制執行における問題点
被告に対する明渡を命じる判決が下されても、被告が任意に明け渡さない場合や、被告が行方不明の場合には、明渡の強制執行手続により明け渡しを実現する必要があります。明け渡しの強制執行手続きを経ないで、被告の同意を得ることなく、建物の中の荷物を撤去したり、土地上の建物を収去したり、部屋の鍵を交換する行為は、原則として自力救済として違法となり、民法上の不法行為を構成することになります。
明渡強制執行の手続きは、一般的には、
① 明渡強制執行の申立
② 事前準備
③ 明渡催告
④ 断行手続
以上の流れをとります。
明渡強制執行の手続きは、正確には、執行官に対する、不動産の明渡又は引渡しを求める手続です。全体として、裁判所の執行官の主導により手続きが行われますので、執行官とのコミュニケーションをとることが大切です。
また、全体の流れの中では、事前準備が重要となります。事前準備においては、開錠の際の業者、執行業者、立会人の手配といったものが必要ですが、これらの業者を知らなければ執行官が手配してくれます。
加えて、明渡催告等の手続きの中で、債務者が要保護者であった場合(例えば重病を患っている場合や認知症の方、子供がいる家庭)については、行政機関の連携が必要です。執行官が連携の手配してくれることも多いですが、執行官によってはこの点を事実上債権者の判断に委ねる場合があるので、事前に調整が必要な場合があります。要保護者がいる場合には、断行手続がいわゆる過酷執行として不能とされる場合があり、この場合には一からやり直しになりますので、注意が必要です(但し、執行不能になった場合でも、行政機関の連携等により任意退去が実現する場合がほとんどです)。
次のページ:【明渡請求訴訟事件の実務】3 相手方への配慮
目次
- (表紙)家賃滞納に基づく明渡訴訟について弁護士が解説します
- 【明渡請求訴訟事件の実務】1 建物明渡請求訴訟の全体像
- 【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (1) 迅速性
- 【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (2)当事者の特定
- 【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (3)物件の特定
- 【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (4)送達の問題
- 【明渡請求訴訟事件の実務】2 明渡請求訴訟の特徴 (5)強制執行における問題点(本ページ)
- 【明渡請求訴訟事件の実務】3 相手方への配慮
- 【明渡請求訴訟事件の実務】4 弁護士相談のタイミングと弁護士相談の前に行うべきこと
- 【明渡請求訴訟事件の実務】5 弁護士に依頼するのに適した案件
- 【明渡請求訴訟事件の実務】6 弁護士相談の際の留意点(必要資料と解決方法)
- 【明渡請求訴訟事件の実務】7 明渡請求の当事者の検討
- 【明渡請求訴訟事件の実務】8 請求権者(賃貸人・所有者)の特定(1)
- 【明渡請求訴訟事件の実務】9 請求権者(賃貸人・所有者)の特定(2)
- 【明渡請求訴訟事件の実務】10 明渡対象物件の特定
- 【明渡請求訴訟事件の実務】11 相手方との交渉
- 【明渡請求訴訟事件の実務】12 訴訟提起の判断基準
- 【明渡請求訴訟事件の実務】13 占有移転禁止の仮処分の要否
- 【明渡請求訴訟事件の実務】14 訴訟提起にあたっての考慮事項(手段選択)
- 【明渡請求訴訟事件の実務】15 訴訟手続~①訴えの提起「管轄・手数料」~